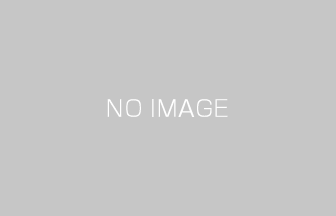新しい床に替えたいけれど、天然木のぬくもりは残したいし、耐久性や寸法安定性も譲れない。
無垢材の風合いをできるだけ手軽に楽しみつつ、乾燥や湿度変化による反りや隙間を避けたい。
床材選びをしていると、難しさを感じてしまうかもしれません。
床材選びの中で価格を抑えたいとなると、挽き板フローリングはまさに願ったり叶ったりの選択肢になります。
本記事では、挽き板フローリングの基本から、朝日ウッドテック、イクタ、大建工業、ウッドワンといった主要メーカーの特徴を詳しく解説し、実際にどの製品を選べばいいのかがすっと腑に落ちる構成でお届けします。
挽き板フローリングとはどんな素材か
挽き板フローリングは、床材の表面に天然木を薄くスライスした挽き板を貼り合わせた複合構造が特徴です。
基材には合板や高密度繊維板(HDF)を用いるため、無垢材に比べて収縮や反りが生じにくく、寸法安定性に優れています。
天然木の厚みはおよそ0.5~3ミリ程度で、無垢材の深い質感や木目の美しさを手軽に取り入れられる一方、価格を抑えつつ施工性の良さも兼ね備えているため、リフォーム初心者からプロまで幅広く支持されています。
挽き板フローリングの構造と特徴
挽き板フローリングの最大の魅力は、基材の強度と天然木の美観を両立できる点です。
まず床下地や既存の下地に直接貼ることができる薄型モデルも多く、厚みが10ミリ未満という製品も存在します。
耐水性を高めた特殊コーティングを施すものや、紫外線硬化塗装(UV塗装)によって傷や汚れに強い表面を実現した製品もあります。
無垢材に比べて反りや隙間のリスクが低く、床暖房対応モデルが豊富に揃うため、寒冷地や高温多湿の地域でも安心して使えます。
無垢材や突板との違い
無垢材フローリングは天然木をそのまま利用するため、使い込むほどに色やツヤが深まる経年変化を楽しめる一方、湿度変化による伸縮や反りへの対策が必須です。
突板フローリングは、さらに挽き板より薄い0.2~0.6ミリほどの天然木を貼るため、コストを抑えながらも一見無垢材のような見た目を再現できますが、挽き板に比べると再研磨や補修の余地が少ない場合があります。
挽き板は厚みがある分、多少の傷がついても表面を削って補修できる製品が多く、長期的なメンテナンス性にも優れているのが大きな利点です。
主な挽き板フローリングメーカーと製品特徴
日本国内で挽き板フローリングを主力製品として展開しているメーカーには、朝日ウッドテック、イクタ、大建工業、ウッドワンがあります。
それぞれ長い歴史と独自技術を持ち、製品ラインナップや表面塗装、挽き板の厚み、施工性に細かな違いがあります。
ここからは各社の代表シリーズを挙げ、その特徴を詳しく見ていきます。
朝日ウッドテックのLive Natural Premiumシリーズ
朝日ウッドテックは創業時から銘木専門問屋を出自とし、天然木の魅力を最大限に活かす技術に定評があります。
Live Natural Premiumシリーズは厚さ1.2~2.0ミリの挽き板を使用し、表面は紫外線硬化塗装で傷に強く仕上げられています。
床暖房対応モデルもあり、表面の凹凸や色ムラが自然木に近い質感を再現。無垢材の持つ温かみと、頑丈な複合構造を両立させたいユーザーに最適です。
イクタの銘木フロアーラスティックシリーズ
イクタは150年以上の歴史を持つ老舗で、銘木を惜しみなく挽き板に使った製品が人気です。
銘木フロアーラスティックシリーズでは、ナラやチェリーなどの厚み3ミリ前後の挽き板を貼り合わせ、挽き板が厚い分だけ削って仕上げ直すことも可能です。
さらにヴィンテージ風の加工を施したビンテージフロアーラスティックなど、多彩な木目デザインをラインナップし、重厚感ある空間演出を得意とします。
大建工業のトリニティシリーズ
大建工業のトリニティシリーズは、見た目からは無垢材と見紛うほどのリアルな木目と質感を持つ挽き板フローリングです。
基材には高密度繊維板を用い、耐水性や耐傷性を高めるWPC(木質プラスチック複合)加工を施したモデルもあります。
3ミリ前後の挽き板は天然木の表情を存分に味わえる一方、複合構造によって反りや伸縮を抑え、さまざまな住宅環境に適応します。
ウッドワンのコンビットモノ 挽板3.0
ウッドワンは天然木無垢材をはじめ、挽き板フローリングにも力を入れるメーカーです。
コンビットモノ 挽板3.0はその名の通り3ミリ厚の挽き板を基材に貼り、オークやウォールナットなどの銘木を贅沢に活かしています。
表面はUV塗装で耐久性と光沢を確保しつつ、木目の凹凸感はそのまま残すため、素足で歩いたときの感触も自然。傷や汚れに強い一方、必要に応じて軽い補修ができるメリットがあります。
その他の注目ブランド
LIXILやWOODONE、NODAなども挽き板フローリングを扱いますが、素材の供給ルートや塗装技術、価格帯に違いがあります。
LIXILは抗菌・抗ウイルス機能を持つ塗装を施したモデルを、WOODONEは自社製材による無垢感の強い挽き板を、NODAはリーズナブルな価格で多彩な色柄を提供するなど、用途や予算に合わせた選択肢が広がっています。
挽き板フローリングメーカー比較表
| メーカー | 代表シリーズ | 挽き板厚 | 主な特徴 | 6畳材料費の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 朝日ウッドテック | Live Natural Premium | 1.2~2.0mm | UV硬化塗装で傷に強く、床暖房対応。無垢同等の質感再現。 | 約12~18万円 |
| イクタ | 銘木フロアーラスティック/ビンテージ | 約3.0mm | 厚挽き板で削り直し可能。ヴィンテージ加工で重厚感。 | 約15~20万円 |
| 大建工業 | トリニティ | 約3.0mm | WPC加工で耐水耐傷性強化。高密度基材で反り抑制。 | 約13~17万円 |
| ウッドワン | コンビットモノ 挽板3.0 | 3.0mm | 天然木銘木を贅沢に使用。UV塗装で光沢と耐久性を両立。 | 約14~19万円 |
挽き板フローリングの選び方と注意点
挽き板フローリングを選ぶ際は、見た目のデザインだけでなく、挽き板の厚みや表面塗装の種類、基材の性能を総合的に評価することが大切です。
厚めの挽き板は再研磨や補修がしやすい反面、価格が高くなる傾向があります。
UV塗装やWPC加工などの表面仕上げは耐傷性や耐水性を向上させますが、メンテナンス方法が製品ごとに異なるため、施工前にメーカー推奨の手入れ方法をしっかり確認しましょう。
メーカー別の強みを活かす選択法
朝日ウッドテックは無垢に近い風合いを重視するなら、イクタは厚みを生かした経年変化を楽しみたいなら、大建工業は耐傷・耐水性を優先するなら、ウッドワンは銘木の香りと質感を大切にしたいなら、と目的に合わせてメーカーを選ぶと失敗が少なくなります。ショールームで実際に触れ、足裏に感じる凹凸や塗膜の硬さを体感して比較しましょう。
施工性とメンテナンスのポイント
薄型モデルやクリック式ジョイントを採用する製品はDIY施工にも向いていますが、含水率管理や下地調整が不十分だと反りや隙間が生じることがあります。
専門業者に依頼する場合は見積もりの際に挽き板の厚みや表面塗装、下地補強の有無などを確認し、追加費用の有無を明確にしておくと安心です。
日常の掃除は中性洗剤を薄めた水拭きで済み、傷や汚れが深刻な場合は製品によってはサンディングと再塗装が可能です。
コストパフォーマンスと長期使用の視点
厚挽き板のモデルは初期費用が高めですが、数十年単位で使用し、再研磨で表面を蘇らせられる点を考慮すると長期的なコストパフォーマンスは良好です。
一方、薄い挽き板モデルは価格が抑えられ、施工費も軽減できるため、ライフスタイルの変化に合わせて張り替え頻度を前提に選びたい場合に向いています。
床暖房対応の有無や抗菌・抗ウイルス機能なども含め、ライフステージに合わせた最適な選択を行いましょう。
導入事例:挽き板フローリングが映える空間づくり
リビングでの活用例
広いリビングに厚み3ミリのナラ挽き板を採用した事例では、無垢材同等の深い木目が空間に落ち着きをもたらし、家具を問わずインテリアに自然に馴染みました。
傷や汚れがつきにくいUV塗装モデルを選ぶことで、子どもの遊び場としても安心して使えると好評です。
子ども部屋・書斎での活用例
子ども部屋には耐傷性が高いWPC加工の挽き板フローリングを敷き、学習机や玩具の落下によるダメージを軽減。
書斎にはチェリー材の銘木挽き板を使い、暖かな木目が集中力を高める効果を狙いました。どちらも年月が経つほど愛着が湧く経年変化を楽しめる点が、後悔しないポイントです。
上質な住まいを実現するために
挽き板フローリングは天然木の質感を手軽に取り入れつつ、無垢材に比べて反りや隙間が出にくい安定性が魅力です。
朝日ウッドテック、イクタ、大建工業、ウッドワンといった主要メーカーはそれぞれに独自の挽き板厚や表面加工、基材構造を持ち、用途や予算、施工環境に合わせた選択肢が豊富に揃っています。
ショールームやサンプルで実物を確かめ、メンテナンス方法や施工費まで含めたトータルコストを比較検討することで、理想の床材を手に入れて末永く快適な住まいを実現してください。