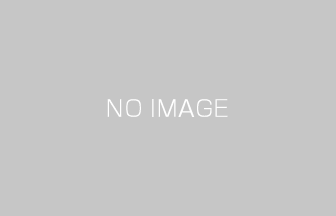置床(おきゆか)は、鉄筋コンクリート造の建物で採用される床工法のひとつで、床スラブの上に支持脚と床パネルを設置し、その上に化粧床(フローリングなど)を張る構造です。
乾式二重床としても知られ、遮音性や保温性、配線・配管の取り回しの自由度が高さが評価され、マンションやオフィスビル、店舗など幅広く採用されています。
この記事では特に置床の「最低高さ」に着目し、その仕様や選び方、注意点について詳しく解説します。
置床における最低高さとは?
置床の最低床高さとは、支持脚を最も低い状態に調整したときの、スラブから床仕上げ面までの高さを指します。
この最低高さは、製品によって異なりますが、低床仕様の製品ではかなり薄い構造で施工が可能となっており、天井高さが限られる場所や床下空間をあまり確保できないケースで重宝されます。
製品による最低高さの例
- 低床タイプの置床:床高が55mmの製品があります。
- 補足:天井の高さを確保したいリフォームや、バリアフリー化に適しています。
- フリーフロアーCP-F(支持脚CP038使用):床パネル天端で38mmの高さを実現。
- 補足:極端に狭い空間でも二重床構造が可能なため、特殊な設計にも対応できます。
最低高さが小さい製品でも、遮音性や支持力の確保、配管の通しやすさなどのバランスを見極めながら選定する必要があります。
置床の構造と仕組みを知る
置床は、床スラブと化粧床との間に支持脚やパーティクルボードを用いた空間を設け、フロアの水平性と快適性を実現する構造です。
コンクリートスラブに直接貼る直貼り工法と異なり、床全体を”浮かせる”構造になっているため、様々な利点があります。
支持脚の役割と高さ調整
- 支持脚には高さ調整機能があり、ミリ単位でのレベル出しが可能です。
- 防振ゴム付きの支持脚を採用することで、遮音効果が高まります。
- 調整可能な高さ範囲の中でも、どこまで低くできるかが設計自由度に関わります。
高さ調整が可能であることにより、床スラブ面の不陸にも柔軟に対応可能です。
置床の最低高さが重要となる場面
最低高さの選定は、空間設計やリフォーム計画において非常に重要です。
特に下記のような場面で最小床高を意識する必要があります。
天井高さが制限されている物件
- 古いマンションやリノベーション物件では、天井高が低いことが多く、床を上げると圧迫感が出やすいです。
- 最低床高が低い製品であれば、室内の快適性を保ちつつ、床下機能を導入できます。
バリアフリー設計や段差解消
- 玄関や浴室、トイレなど段差が生じやすい場所では、低床置床が活躍します。
- スロープや手すりとの取り合いもスムーズになるメリットがあります。
最低高さ以外に確認すべきポイント
最低高さだけに注目するのではなく、他にも確認すべき要素があります。
耐荷重性能
- 薄型の製品ほど支持脚やボードの強度に注意が必要です。
- 住宅であれば180kg/m²程度が基準ですが、重い家具や設備がある場合はさらに高い耐荷重が必要です。
施工性と対応力
- 部屋の形状が複雑な場合は、支持脚の配置が難しくなるため、柔軟な対応ができる製品を選ぶべきです。
- 接着剤不要で施工できるタイプは、工期短縮にもつながります。
置床の最低高さは快適さと機能性のカギ
置床の最低高さは、ただの寸法ではなく、設計の自由度や住空間の快適性に大きく影響する要素です。
天井の高さ、用途、構造に応じて、最適な最低床高を持つ製品を選ぶことで、快適で機能的な床づくりが可能になります。
設計段階から床高を意識して、空間全体のバランスを見ながら計画することが成功のカギです。